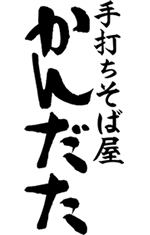●小野小町は平安時代に生きた女性。
絶世の美女として、
千年以上経った今も、その名が伝えられている。
よく、美人がいると、
○○小町などと、はやし立てられたという話も、
最近まであったこと。
よっぽどの美人だったのだろう。
さて、その小野小町は、
秋田県の出身だそうだ。
秋田と言えば「秋田美人」。
色の白い人が多いそうだ。
ご丁寧に、
この肌の白さを測定したお医者さんがいたそうで。
それによると、秋田県の女性の肌は、
全国平均に比べ、かなり、白いことが判明したそうだ。
これは、秋田県の年間の日照時間が、
常に最下位にあることと、
関係があるのだか、、
ないのだか。
昔から言われている言葉。
「色の白いは七難隠す」。
つまり、色が白いと、
少しぐらいの欠点が隠れて、
女性が美しく見える、、、とか。
小野小町も、
きっと、色白の美人であったことだろう。
●さて、長野の人が、
東京へ行ってそばを食べてきた。
そうして、こんなことを言う。
「いやあ、東京のそばは、
白くて、うどんみたいだったよ。」
多分「更級」を召し上がったんだと思ったら、
普通のそばだという。
ははあ、東京のそばは、確かに、
ここ長野で食べられているそばに比べると、
色が白いかもしれない。
ひと昔前には、そばは、色の濃い方が、
そば粉がたくさん使われている、
と思っている人が多かったそうだ。
つまり、色の白いそばは、
小麦粉が、たっぷりと使われているからだと。
実は、そばの色は、
小麦粉の量とは関係がない。
そばの実の内側の部分を使えば白くなるし、
そばの実の外側の部分を使えば濃い色になる。
さらに、殻まで挽き込めば、黒いそばになる。
つまり、そばの色は、
そばの実の、どの部分を使うかによって、
変わって来るのだ。
●その昔、秋田に行った時、
一緒に行った友人が、
駅前の観光案内所で尋ねた。
「あの、どこへ行けば秋田美人に会えますか。」
ひとしきり、大声をあげて笑っていた、
窓口のおばさん。
それでも、道路の向こうを指差して、
「ほら、あそこのデパートに行けば、
たくさん秋田美人がおりますよ。」。
ということで、
デパートで美人鑑賞会。
美人がいたかどうかは、
ちょっと、記憶が曖昧なのだけれど、、、
でも、色白の人の多いことは確か。
さて、秋田は日照時間が少ないから、
色白の人が多いとか。
そばも、光のあたる外側ほど色が濃く、
光の届かない内側は、白っぽい。
その白っぽいところだけを食べたいという、
そう思った人もいるんだね。
そばの実を臼で挽くと、
柔らかい内側の部分から粉になって出てくる。
それが一番粉で、白い色をしている。
それから、やや色付いた二番粉、
そして、さらに色の濃い三番粉が出てくる。
それじゃあ、一番粉だけでそばを作れば、
真っ白なそばが出来るはず。
ところが、ところが、そうもいかない。
この粉は、確かに色は白いが、
そばかすだらけなのだ。
つまり、ホシと呼ばれる黒い点が混ざってしまうのだ。
●もっと、色白の、美人のそばに出会いたい。
秋田に一緒に行った友人みたいな、
そんな思いの人たちが、
工夫をしてみたんだ。
そうして、そば粒を粗く割ってから、
そばの芽の部分や不純物を取り除き、
臼を浮かせるようにして挽いて、
そばかすのない、真っ白な粉を作り出したんだね。
これが「更級(さらしな)」。
江戸時代から作られていたが、
技術が確定したのは、明治になってからだそうだ。
美人が扱いにくいように、(よく知りませんが)
この粉も、そばに打つのがちょっと難しい。
だから、湯ごねという方法で、
そばを打つのだ。
さらに、薄く延ばす難しさがあって、
職人の腕の見せ所とばかり、
細打ちにしたりする。
私も「更級」を作るけれど、美人を前にして、
ちょっと、包丁が乱れ気味。
でも、ほら、
色が白いは、、、
ええ、私のは七難じゃなくて、
百難だから、隠しきれないって?
●色白の美人には、化粧も引き立つ。
だから、この更級にも、
化粧、、、いや、
さまざまな変わりそばが似合うのだね。
お茶の緑、エビの赤、タマゴの黄色、
ごまの黒等と、鮮やかな色を楽しむそばもある。
柚子切り、桜切りなどの、香りを楽しむそばもある。
近頃、こういう変わりそばを用意しているそば屋が、
けっこう増えてきているようだ。
そんな、遊び心に付き合うのも楽しい。
「手打ちそば屋 かんだた」でも、
ちょっと、今までとはちがう、
そばの味のしっかりとする「更級」をお出ししている。
色も真っ白ではなく、
ちょっと、黄色がかった、落ち着いた感じ。
甘味の乗った、美人のそばだ。
だったら、
「小町そば」という名前に変えようか、
今考えているところ。
んっ、「小町」が泣くって。
2016年08月
そば屋とわかる佇まいとは
●ごく、個人的な思い出を、
語らせていただきたい。
私が小学校低学年ぐらいの頃の話。
時代にすると、東京オリンピックの、
ほんの少し前のころ。
学校にいるときに、歯が痛み出してしまった。
帰っても痛くてしょうがない。
歯医者にいこうと思ったが、
今まで行っていた、近所の歯医者は、
先生が高齢のため、診察を止めてしまったのだ。
その歯医者は、家のすぐ裏にあり、
いわゆる、昔風の洋館といわれる建物だった。
重苦しい石の塀に囲まれ、
入り口には、ヤツデが生い茂っていた。
建物の入り口の扉は、
真ちゅうの大きな取っ手が付いていて、
曇りガラスに金文字で大きく、
「○○歯科醫院」と書いてあった。
横には「醫学博士××××」という、
黒地に金文字の額まで飾られていた。
中に入ると靴を脱ぎ、すぐ右側の階段を上る。
二階が、当時としては洒落た出窓のある診療室で、
恐ろしく大きな音のするドリルで、
歯を削られたものだった。
私は、小さい頃から、この歯医者に厄介になっていた。
そこが、診察をしなくなってしまったのだ。
でも、歯が痛くて仕方が無い。
兄が、商店街の向こうに、歯医者があるというので、
初めてのところだが、一人で行ってみることにした。
●教えられた通りを行くと、
なるほど、歯医者らしい建物があった。
石の塀で囲まれ、どっしりとした洋館風。
ちょっと間口が狭いけれど、ヤツデも生い茂っている。
扉のガラスには「○○醫院」と金文字で書かれている。
でも、その横に書かれていた文字は、
ちょっと難しくて読めなかった。
とにかく歯が痛いのだ。
知らないお医者さんでもいいから、診てもらおう。
中に入ると、すぐ待合室で、
何人かの人が待っていた。
靴を脱いで、座って待っていると、
やがて、看護婦さんに呼ばれる。
診察室に入ると、普通の丸いいすに坐らせられる。
あれ、脇に流しの付いた、
大きないすじゃないの。
あの、無気味なドリルの姿が無い。
女性のお医者さんが私に聞く。
「ぼく、どうしたの。」
「歯が痛いのです。」
そうしたら、女医さんは、不思議そうな顔をして聞く。
「どうして、歯医者さんに行かないの。」
その時になって、やっと、周りの状況に気付いた私。
「えっ、ここは、歯医者さんじゃないの?」
そのとたんに起こった周囲の大爆笑。
先生なんか、いすから転げ落ちんばかりだし、
看護婦さんも、他の患者さんも腹をかかえている。
保険証を返してくれた、受付のおばさんも大笑い。
わたしは、歯の痛みをこらえながら、
身を隠す穴も探せなかった。トホホ。
歯医者は、その医院の手前にあった。
きれいな、クリーム色の壁に、青い扉の建物だった。
上の方に歯科の看板が付いていたのだが、
小さな子供には、目に入らなかったようだ。
というか、その建物のイメージが、
その時の私には、とても歯医者とは感じられなかったのだ。
大笑いされて、初めて「耳鼻咽喉科」の意味を知った。
以降、今の歳になるまで、この科の医院は、
避けて通っている。
●人から聞いた話。
その人の近所に新しい店が出来たそうだ。
オシャレな外観で、何やら横文字で書いてある。
中で、お茶を飲んでいる人の姿が見えるので、
てっきり喫茶店だと思っていた。
あるとき、ちょっと喉が渇いたので、
その店にでも寄ってみようかと思って良く見たら、
そこは、喫茶店、、、、、ではなく、
美容院だった、、、そうだ。
人の先入観というものは恐ろしい。
いくら、看板に、「○○屋」と書いてあっても、
パッと見た目で、どんな店なのか思い込んでしまうのだ。
食べ物屋であれば、
店の外見で、どんなものを扱っている店なのか、
高い店なのか、大衆的な店なのかを読み取ってしまうのだ。
●そば屋も、
パッと見たとたんに、
そば屋と分かるような店構えをしているだろうか。
遠くから見ても、
あっ、あれはそば屋だと思われるような店構えが
できるといいのだろうなあ。
何がそば屋らしいたたずまいなのか、
そう言われると、ちょっと困るけれど。
そば屋らしいといえば、
大きめの暖簾、
屋根の張り出した和風の建物、
灯籠形の招き看板、
棚には使えそうもない曲がりくねった板(銘板というらしい)に書かれた達筆の店名。
などなど。
手打ちの店であれば、打ち場が見えているといいのかもしれない。
ところが、この頃は、まったくそば屋さんらしくない雰囲気の、
そば屋さんもあるようだ。
外見はまるでオシャレなダイニング、そこに「そば」の看板を出すところもあるそうだ。
ふうん、そば屋らしさって、何なのだろう。
それぞれの店で、それなりの工夫をしているのだろうねえ。
●人は、それぞれに、
思い込みというものがある。
一度そう思い込むと、
なかなか、その思いから抜け出さないのだ。
「手打ちそば屋かんだた」に、たまに、
路地の入り口にある韓国料理店と間違えて入ってきて、
「韓国ラーメンを下さい。」と言う人がいたとしても、
決して笑ってはいけない。
雰囲気で分かりそうなものだろうなんて言ってもいけない。
思い込みと言うのは、強いものなのだ。
少なくとも、あの女医さんのように、
いすから転げんばかりに、
笑いこけてはいけないのだ。
そばの相撲
●お客さまの中には、そばをお好きで、
ずいぶんとたくさん召し上がる方がいらっしゃる。
こんなに、食べられるかなあ、
と思って見ていても、
ちゃんと、お腹の中に入るので不思議だ。
いったいそばは、どのくらい食べれるものだろうか。
そんな、食べ比べは、昔からあったようだ。
例えば、落語の「そば清」。
そば好きの清兵衛さんは、
そば屋で何枚食べられるかを賭けて、
いつも、掛け金をいただいていく。
ところが、ある時、
今まで食べたことのない量を食べさせられる。
さすがに苦しくなった清兵衛さん、
信州で仕入れてきた、ある薬を使うのだ。
その薬と言うのが、実は、、、、、。
まあ、このように、大食いを自慢する人は、
いつの時代にもいるようだ。
●さて、時代は江戸時代中頃、
あるところで、「そばの相撲」が、
大勢の見物人の前で開かれた。
そば喰い自慢の二人、谷村氏と平岡氏の、
どちらの方が、たくさん食べれるかを競うものだった。
二人の前に、それぞれ、
一升以上のそばが盛られた大重箱が置かれ、
勝負は始まった。
それだけでも、かなりの量だ。
食べきれるだろうか。
大勢が見守るなか、
しかし、ふたりは、楽々とその重箱を空けてしまう。
驚いた見物人。
そうして、さらに、椀に盛ったそばを食べ始めたのだ。
さて、このあまりの勢いに、
どちらが勝つかと、楽しみにしていた見物人、
今度は、
そんなに食べて大丈夫なのかと心配になって来た。
二人が21椀づつ食べたところで、
双方とも充分に食べたという。
これ以上は、かえって興ざめになるので、
そばの相撲は、同じ量を食べて、
両者引き分けということになった。
やんやの喝采を浴びた両人。
●ところが、ある人が二人に尋ねた。
ちょうどそら豆ご飯が炊きあがっているが、
食べてみるかと。
ええっ、たっぷりのそばを食べたばかりに、
「そら豆ご飯」だなんて。
そうしたら、平岡氏が答える。
これは珍しい。いただきましょう。
そうして、大盛り二杯のそら豆ご飯を食べてしまったのだ。
人々は呆気にとられて、
肝を潰したそうだ。
そうして、ある人が言う。
そばの量は同じでも、そら豆ご飯を食べた分だけ、
平岡氏の勝ちだと。
人々は沸いたが、
すぐに反論があった。
これはそばの勝負なので、他のものは入れないほうがいい。
結局、そういう意見が多く、
この相撲は勝負なしと言うことになったそうだ。
でも、人々は、平岡氏の大きな胃袋に、
恐れをなしたそうだ。
●こういうそばの食べ比べは、
いまでも、各地で行われている。
長野でも、戸隠のそば祭りの時に、
そば喰いコンクールが行われていた。
でも、さまざまな事情があって、
数年前から取り止めになった。
そばを食べる量より、
そばの質を大切にしたいという、
そば屋の店主たちの思いがあるようだ。
そばの食べ比べでは有名な、
岩手の「わんこそば」。
小さなお椀に盛られたそばの、
食べた数を競うものだ。
盛岡市ではその名もすごい、
「全日本わんこそば選手権」なるものが、
毎年開かれている。
今までの最高が、時間無制限時代の(今は15分)、
559杯。
説明によると、10杯で、
軽めのせいろ一枚分ぐらいだというから、
せいろで55枚分。
え〜、え〜!!!!。
どこに入るのだろう。
●江戸時代に行われた「そばの相撲」。
実は、こんな後日談がある。
そばを食べたあと、そら豆ご飯を食べた平岡氏。
一、二年後に、内臓を痛めて、
長く患い、とうとう亡くなってしまったそうだ。
一方の、谷村氏。
好きなそばを食べながら長生きしたそうだ。
まあ、好きなものを、腹一杯食べるのもいいけれど、
ほどほどということも、
大切なようで。
夏のそばを「まずい」とはいわせない
●私が若い頃、
そばの評論を読むと、
必ず、夏のそばの悪口が書かれていた。
いわく、
「梅雨を越えたそばは、
臭くて食べられない。」
「夏の暑い季節に、
そばを食べる奴の気が知れない。」
あれあれ、随分なことを言っている。
さらに、こんなことを言う人も。
「まずいそばを出すぐらいなら、
夏から新そばまでの間、
店を閉じてしまうのが、
真っ当なそば屋だ。」
すみません。
「かんだた」は真夏も営業している、
「真っ当でないそば屋」で。
●私の子供の頃、
そば屋では、夏になると、
麦切り(冷や麦)を出していたような記憶がある。
それと一緒にそばを食べると、
確かに、独特の蒸れた匂いを、
子供心に感じたものだ。
夏目漱石の「我輩は猫である」の中でも、
猫の主人が、
そばを取り寄せた友人の迷亭先生に、
こう言っている。
「君、この暑いのにそばは毒だぜ。」
夏の暑い季節は、
あまり、そばを食べるものでは、
なかったようだ。
●ところがどうだろう。
昔の人が言うように、
今でも夏のそばはまずいのだろうか。
少なくとも、
あの独特の蒸れた匂いのするそばを出すところは、
町中のそば屋であろうが、手打ちそば店であろうが、
駅のそばであろうが、観光地のそば屋であろうが、
コンビニのそばだろうが、
まず、見当たらない。
それどころか、熟成された分だけ、
味の濃いおいしさがあるような気がする。
新そばのころが、生意気な高校生とすれば、
夏のそばは、多少世の中を知り始めた、
野心的な好青年というところか。
いや、けっして、脂ぎったおじさんや、
人生を悟って枯れて来たおじいさんではない。
まだまだ、若さの香りのする年頃だ。
夏の季節だって、
しっかりと香りのするそばが食べられるのだ。
なのにどうして、昔の人は、
夏のそばを、あんなに嫌ったのだろう。
●先日、あるところでそばを食べて、
久しぶりに、あの蒸れたような匂いを嗅いだ。
それは、玄そばを水に浸け、芽を出したところを、
粉にしたそば。
それはそれで、なかなか味わいのあるものだった。
でも、あの、子供の頃に嗅いだ、
独特の匂いを思い出させてくれたのだ。
つまり、昔は、夏になると、
芽の出かかったそばを食べさせられていたようだ。
きっと、当時は、玄そばの保管状況が悪く、
梅雨の湿気でそばが芽を出そうと、
動き始めていたのだろう。
それで、風味が変わって、
敬遠されるようになったのかも知れない。
●さて今は、
玄そばの保存もよくなって、
特に、湿気に注意することによって、
夏でも、おいしいそばが食べられるようになった。
といっても、けっして、冷蔵庫のような、
低い温度で、保管するわけではないらしい。
ある程度の温度を、変化のないように保つのだそうだ。
そば粉屋さんの話では、
あまり、温度が低すぎても、そばが眠ってしまい、
かえって風味が落ちるそうだ。
つまり、玄そばが、
眠るでもなく、目覚めるでもなく、
うつらうつらとしている状態で、
保存しておくのがいいらしい。
まあ、業者さんによって、
さまざまな工夫があるようだ。
夏のそばがおいしくなったのは、
厨房の設備の変化も
多少はあるかも知れない。
昔は、今のように冷蔵庫や、
冷水、氷を気軽に使えなかったからね。
そうそう、それに、
大汗をかきながら、
しっかりとしたそばを打っている、
私達職人の力も、、、
ほんの少しは、、、、
ごく微量に、、、、
あっ、関係ないそうだ。
●今でも、「そば通」の方々の中には、
「夏のそばなんか、、、、」と言われる方も、
いらっしゃるようだ。
でも、さまざまな工夫により、
夏だって、おいしいそばが、
食べられるようになったのだ。
夏のそばが「まずい」とは言わせない。
この季節には、この季節なりの、
おいしさがあるのだ。
そういう思いで、
ともすれば気難しい、
夏のそばを、しっかりと打ちたいと思う。
でも、
夏から新そばまで、
店を畳んでしまうという、
「真っ当なそば屋」にも、
う〜ん、惹かれるなあ。
いや、いや、
けっして、サボりたいと言っている訳では、、、、
、、、ありません。
とかく、そば好きってやつは
●都会の真ん中の、
とあるビルの階段を下りたところにある、
しゃれた内装のそば店。
夜ともなると、
間接照明で浮き上がる店内にはジャズが流れ、
落ち着いた雰囲気の中で、
それなりの身なりの人たちが、
そばを楽しんでいる。
おりしも、その一角の、
一番奥まったテーブル席では、
背広姿の若い男Aと、
洗練されたスーツを着た女Bが、注文したそばが、
出てくるのを待っている。
この二人、
夫婦というほどの、あきらめの中に落ち着いた関係ではない。
婚約者という、幻想に包まれた仲でもない。
恋人という、非経済的な関係の、
なおかつ、その初心者同士のようだ。
●店員に案内されたときから、
どうも、女Bの機嫌は悪い。
「せっかくの私の誕生日なのに、
どうしてまたそば屋なの。
そのうえ、これから会社に戻って、
残業があるなんて。
ひどいわ〜。ひどいわ〜。」
ひたすら謝る男A。
「私だって、責任のある仕事をしているから、
仕事の大切なことは分かるけれど、
少しは私のことを考えてもらいたいわ。」
ひたすら謝る男A。
「この前だって、、、、
(あまり意味の無いことが多いので省略)
なのよ。」
ここで男Aの反撃。
「いや、だから、ここのそば屋を予約しておいんだ。
ここのそば屋は人気で、この時間には、
いつも満席なんだよ。
だから、仕事の合間でも、
君にここのそばを食べさせたいと思ってね。」
女B、冷たく男Aを見る。
「あなたが食べたかっただけでしょう。」
●ここで店員がそばのせいろを持って登場。
「お待たせしました。
本日のおそばは、長野県の信更(しんこう)の産です。」
女Bは言葉を止めない。
「だからね、少しは私の話も聞いて欲しいわ。
(グチ、グチ、グチ。)」
男A。
「とにかく、その話は、そばを食べてからにしよう。
そばは、茹でたてが一番おいしいのだから。」
女B(キッとした表情で)。
「私の話より、そばの方が大事なの?」
男A
「いや、まずはそばを食べてから。
その話は、また後から聞くよ。
ほら、見てごらん、信更のそばだって、
いい艶をしている。」
女B
「私の話は途中なのよ。
せめて、最後まで聞いてよ。」
男A(そばに箸をかけながら)
「うん、食べながら聞くから。
う〜ん、おいしそうだ。」
ズズーっ、ズズーぅ。
女B(一瞬、そのきれいな栗色の髪が逆立つ)。
「うも〜〜〜お。」
牛が鳴いたか、カエルがひっくり返ったか、
はたまた新興宗教の呪文か。
●女B、すっと席を立ち、
やたら黒光りする大きめのハンドバッグを手に、
足音も荒く立ち去る。
男A、慌てて、立ち上がって、
その後を追いかけようとするが、
左手に持ったそば猪口と、
右手の箸に気付く。
そして、女Bの背中が1.5秒ほどで見えなくなると、
おずおずと席に座り直した。
そのまま5秒ほど固まっていたが、
不意に、思い出したように、
残りのそばをたぐり始める。
ズズーっ、ズズーぅ。
店員が、何も知らずに
そば湯の入った湯桶をおいていく。
男A、食べ終わって、
その湯桶を持ち上げようとしたが、
ふっと気付いてそれをおろす。
周りを一瞬見回すと、
女Bが、手を付けずに立ち去ったせいろを、
空になった自分のと、そっと入れ替える。
そして、そのそばを、たぐる。
ズズーっ、ズズーぅ。
そうして、満足そうな笑みを、
口元から2センチほどのところに浮かべる
男Aなのであった。
その時店内には、
ルイ・アームストロングの
「この素晴らしき世界(What a Wonderful World)」が
流れていた。
ん〜〜ん、全くそば好きってやつはねえ。